 まいた家のタケオ(父)
まいた家のタケオ(父)どうも、2022年に娘が産まれ2025年からこのブログを運営しているまいた家のタケオ(2児の父)です。このブログでは、実際に子育てをする中で気づいた育児術や食育に関して発信しています。
まいた家で実践しているおむつ無し育児について紹介します!
「おむつ無し育児」って、最近ちょこちょこ耳にするけど、一体どんなことをするの?



おむつ無し=ずっとスッポンポンで過ごすの?
良い効果があると言われてもハードル高そうだし、イメージ湧かないな・・・
実はまいた家でも半信半疑でしたが、できることから少しずつ始めてみました。
とはいえ、最初から布おむつにしたり、おむつを完全になくしたわけではありません。
「あ、今おしっこしそうかも?」というタイミングで紙おむつを外して、トイレやおまるでさせてみる。
それだけのシンプルなスタートでした。
むしろ初心者さんには、紙オムツだけで気楽に始める方法をおすすめしたいです。
赤ちゃんのサインに気づいたら、紙オムツを外してさせてみる。うまくいったら「ラッキー!紙オムツ1枚浮いた♪」くらいの気持ちでOKです。
「おむつ無し育児」は、完璧を目指すよりも、赤ちゃんとのやりとりを楽しみながら、できる範囲でゆる〜く取り入れていくのがコツです。
これから始めてみたい人も、すでにトイトレを意識しているパパママも、きっとヒントになる情報があるはずです。
ぜひ最後まで読んでみてください!



成分分析に関わる研究職お父さん。
食品の安全性や栄養、農薬、遺伝子組み換えなどについて
専門的な視点から、やさしくわかりやすく発信。
子育て中の2児の父として、安心できる食選びや5感を刺激する育児も日々実践中!
「BLW離乳食ってどうやるの?」
「成分表示ってどこを見ればいい?」
「子連れお出かけ先のおすすめは?」
そんな疑問に答える情報をお届けします。
難しいことをかんたんに。
パパ・ママと一緒に“食の安心”や“育児”を考える場になれたら嬉しいです!
この記事では、実際に我が家で実践している「おむつ無し育児」について、初心者さんにも分かりやすくまとめています。
- おむつ無し育児ってどんな育児スタイル?
- 我が家が始めたきっかけと、最初にやったこと
- 赤ちゃんのサインや声がけのコツ
- おまるの使い方とおすすめグッズ
- 布おむつとの組み合わせ方
- 実際にやって感じたメリットとデメリット
我が家がおむつ無し育児を始めたきっかけ


我が家では、赤ちゃんが生後1ヶ月頃に「おむつ無し育児」をスタートしました。
もともとは、「おむつかぶれが気になるな…」という小さな悩みからでした。おむつをすぐ替えても赤くなってしまったり、ちょっとムズムズしているのか機嫌が悪くなったり。
そんなときにふと目にしたのが、「おむつ無し育児」という言葉。
正直最初は、「いやいや無理でしょ…」と思っていましたが、調べてみると「一部のタイミングだけ」「ゆるくやってOK」というスタイルでも大丈夫ということがわかり、ハードルが一気に下がりました。
さらに興味深かったのが、「赤ちゃんは排泄前にちゃんとサインを出している」という情報。
「泣く」「モゾモゾ動く」「急に静かになる」など、小さな変化に気づくことで、赤ちゃんと“通じ合える感覚”が得られるというのも魅力的でした。
そこから「じゃあ、できるときだけでもやってみようか」と、我が家のおむつ無し育児が始まりました。
まいた家の実践例:おむつ無し育児のやり方
「おむつ無し育児」と聞くと、赤ちゃんの排泄をすべて予測して対応するような難しいイメージがありますが、実際はもっと気軽にできるもの。
まいた家では以下のようなポイントを意識しながら、できるタイミングだけゆるく実践しています。
排泄のタイミングを見極める
我が家で「今かな?」と思う主なタイミングは以下のとおりです。
- 起きた直後(朝・昼寝後)
- 授乳やミルクの後
- お風呂の前



寝起きはかなりの確率でおしっこするよ!
赤ちゃんからのサインを観察する
赤ちゃんは排泄の前に、実はサインを出してくれていることがあります。
まいた家の場合、以下のようなサインがよく見られました。
- ご機嫌に喋って(クーイングして)いたのが急に静かになる
- 不快そうに泣き出す
- モゾモゾ・ソワソワと体を動かす
最初はなかなか分かりづらいですが、毎日観察していると「なんとなくこの動き…もしかして?」とピンとくることもあります。



寝起きはかなりの確率でおしっこするよ!
排泄時の声がけ
トイレや洗面器、補助便座に連れて行ったときは、排泄を促す合図の声かけをしています。
我が家では、以下のような言葉をかけています。
「おしっこしーしー」、「うんちがうーん」
こんな声がけで出るわけないと思っていたのですが、声がけを繰り返していくと、赤ちゃんが排泄する確率が上がりました!
もちろん毎回出るわけではありませんが、出なくてもOK。「トイレで排泄する」という流れを体験させるだけでも十分意味があります。



初めておまるにおしっこさせようとした時、半信半疑で「おしっこシーシー」って言ったら、ほんとに出てビックリしたよ!
繰り返し声がけすると、赤ちゃんにとってそれが排泄するスイッチになるみたいだよ!
排泄はどこでするの?まいた家のおまる活用法
排泄場所については、おむつ無し育児を始めた時期や赤ちゃんの発達段階に応じて、無理のない範囲で工夫してきました。
我が家の場合、小さいうちはおまるの中身(取り外せるポット部分)を単体で使い、大きくなってからはおまる本体に座って排泄するようになりました。
使っていたのは、リッチェル(Richell)の椅子型おまる。座らせやすくて安定感もあり、中身だけを取り外して洗えるのでとても衛生的でした。




乳児の間は親の膝の上に乗せておまるにさせていました(下図のイメージ)。最初は狙い通りにおしっこを入れるのが少し難しいので、タオルやオムツ替えシートなどを敷いた上で洗いやすいように小さな白いおまる部分だけ使うのがオススメです!


おまるに座ることが“遊び”の延長のように感じられたのか、また、保育園で月齢が上のお友達の様子を見て触発されたのか、年齢が上がると(2歳頃)すんなり自らおまるに座ることを受け入れてくれました。
もしこれから始めるなら、我が家でも愛用していたリッチェルの椅子型おまるはおすすめです。仮におむつ無し育児に挫折したとしても、今後来たるトイトレで出番がありますので無駄にはなりません。
出なかったときもOK!気楽に継続
もちろん、「全然思ったタイミングで出なかった!」という日もたくさんあります。
でも、それでも全然OK。「出る/出ない」よりも、赤ちゃんと一緒に“排泄を意識する時間”を共有することに意味があると感じています。
最初は一日1回でも大成功!
親が無理なく続けられる範囲で、楽しく試してみるのがおすすめです。
布おむつとの組み合わせ方
おむつ無し育児は、最初は紙オムツを外して排泄させるだけでも十分です。
「おしっこしそうだな」と思ったタイミングで紙オムツを外して、おまるやトイレでさせる。
うまくいけば紙オムツ1枚節約!ラッキー!という気持ちで、気軽にスタートできます。
紙オムツはずしに慣れてきたら、布おむつを取り入れてみるのもとてもおすすめです。
布おむつのメリット
赤ちゃんが「出た」感覚に気づきやすい
布おむつは紙オムツほど吸水性が高くないため、排泄した直後に濡れた・気持ち悪いという感覚を赤ちゃん自身が感じやすくなります。
これにより、赤ちゃんが排泄を意識しやすくなり、自然とサイン(モゾモゾしたり、泣いたり)を出してくれるようになることが多いです。
経済的&環境にもやさしい
布おむつは簡単に洗って繰り返し使えるので、使い捨ての紙オムツに比べてコストを大幅に抑えることができます。まいた家では始めて1ヶ月程度で紙オムツの消費量が半分以下になりました。
また、ゴミも減るので環境にもGOOD。家計にも地球にもやさしい選択です。
旅行時の荷物が減る
旅行の荷物で特にかさばるのが紙オムツ。現地調達が難しい場合は日数分持って行かなければならないので大変ですよね。
その点布おむつは非常にコンパクト。夜サッと手洗いしてハンガーにかけておけば翌朝には乾くので、特に長期旅行では助かります。
まいた家での使い方
我が家では、普段は布おむつを使用しつつ、排泄サインに気づいたときにおまるやトイレに誘導するスタイルを取っています。
もちろん、外出時や就寝時、気持ちに余裕がない時や体調が悪い時は無理せず紙オムツを使ったりと、そのときの状況に合わせて柔軟に。「布おむつで絶対やらなきゃ!」と気負わず、できる範囲で取り入れるのが継続のコツです。
布おむつ生活に興味が出てきたら、まずは1枚からでも是非試してみてください。毎日紙オムツ代が1枚分浮きます!
まいた家で使っている布おむつ
布おむつ+布おむつカバー


まいた家では布おむつとおむつカバーを合わせて使っています。
布おむつは、肌に優しい綿100%のサラシを使っています。輪っかになっており、洗濯しても乾きやすいのが特徴です。


おむつカバーはkuccaを使用しています。綿100%のダブルガーゼを使用しており、通気性もよく、丈夫で乾きやすいのが特徴です。マジックテープも、ベビー用に特注で制作されているため、柔らかく肌に優しいです。
使い方は簡単。おむつカバーの上に折って縦長にした布おむつをのせ、後はテープタイプのオムツと同様に赤ちゃんにつけるだけです。


kuccaの布おむつカバーにはテープタイプとパンツタイプがあり、小さいうちはテープタイプ、大きくなったらパンツタイプなど赤ちゃんの発達段階にフィットするものを選べます。またデザインも非常に豊富なので、選ぶ楽しみや赤ちゃんが付けた時のオシャレさもあってオススメです!
おむつ無し育児のメリット・デメリットを正直に話します
おむつ無し育児には、たくさんの良い面がありますが、同時に「手間がかかる」「失敗もある」などの現実的な大変さもあります。
実際に取り組んでみて感じたメリットとデメリットを、正直にまとめました。
メリット
1. 赤ちゃんの排泄リズムやサインに気づきやすくなる
毎日観察するうちに、「あ、そろそろおしっこかな?」というタイミングがだんだん分かるようになります。
これによって赤ちゃんとのコミュニケーションがより深まるのが大きなメリット。特に新生児のうちからコミュニケーションが取れる、赤ちゃんの意思を感じるという感覚は手探りで行っている育児の中での喜びや自信につながりました。
2. 赤ちゃん自身が“排泄”を意識するようになる
おむつを外して排泄する経験を積むことで、赤ちゃん自身が「出る前に伝える」意識を持ちやすくなります。
特に布おむつと組み合わせると、出た感覚が分かりやすいため、より早く“トイレ感覚”が育ちやすい傾向があります。
3. 紙オムツ代の節約につながる
毎日数枚でも紙オムツを使わずに済めば、年間で考えるとかなりの節約に。
また、布おむつと併用することで、よりゴミの量も減らせて環境にもやさしいです。
4. おむつ無し育児で、トイトレがスムーズに?
実は、おむつ無し育児をしていた家庭では「トイレトレーニングがスムーズに進んだ」という声が多く聞かれます。
排泄のサインを日常的に読み取り、トイレやおまるで排泄する習慣があると、赤ちゃんにとって「排泄はトイレでするもの」という感覚が自然と身につきやすくなります。
実際に、早い子では2歳前におむつが外れたという報告もあります。海外の研究や伝統的な育児スタイルの中でも、こうした“早めのトイレ習慣”はトイトレをスムーズにすると言われています。
とはいえ、焦らず、赤ちゃんと一緒に楽しむ気持ちが何より大切です。
期待しすぎず「いつかはできるもの」くらいのスタンスで、日々の変化を楽しみながら取り入れてみてください。
参考書籍
『Infant Potty Training: A Gentle and Primeval Method Adapted to Modern Living』ローリー・ブーキー(Laurie Boucke)著
“Many babies whose parents use infant potty training are out of diapers by 12 to 18 months. Some even earlier. This contrasts sharply with the mainstream diapering and potty-training culture, where children often continue using diapers past age 3.”
(訳:おむつなし育児を実践している多くの家庭では、赤ちゃんは12〜18か月でおむつが外れます。中にはもっと早い子もいます。これは、3歳を過ぎてもおむつを使うことの多い一般的な育児文化とは大きな違いです。)
デメリット・注意点
親がしっかりと観察する必要性
赤ちゃんの排泄サインを見逃さないためには、ある程度の“観察力”“注意力”が必要です。
初めのうちは失敗して濡らしてしまうこともありますが、だんだん慣れていくものなのでご安心を。必ず成功させなくてはと思わずに、「サインに気づけたらラッキー!」くらいの感覚でやるのが継続のコツです。
また、忙しい時間帯や時期はどうしても意識が離れがちになります。1日のうち「朝起きてすぐの1回」や、「お風呂上がりから寝るまで」など短時間でも細く長く続けると、親の経験値も上がっていくと思います。



育休中は時間に余裕があったけど、復職すると必然的に子どもと接する時間や余裕は減るよね。それでも帰宅後から就寝まではやってみようと緩く継続したら、月齢による変化(排泄前のサインや、トイレに対する子どもの反応)を見ることができてとても興味深かったよ。
すぐに成果が見えないことも
「すぐにオムツが取れる!」という魔法ではないので、焦らず気長に取り組むことが大切です。
成功の連続というよりは、失敗を含めた“やり取りの積み重ね”が育児の楽しさにつながると思います。
完璧を目指すのではなく、できる範囲で・無理せず取り入れるのが「おむつ無し育児」を続けるコツです。
失敗してもOK!親子で一緒に少しずつ進めていくプロセス自体が、かけがえのない時間に感じました!
おむつ無し育児と合わせてやってよかったこと
おむつ無し育児を始めると、赤ちゃんの排泄サインを意識する分、育児の中でも“観察する時間”や“排泄を手助けする時間”が自然と増えていきます。
その分、家事やほかのことに使える時間は限られてくるので、育児以外のところはなるべく楽するのがまいた家のスタイルです。
食材宅配の活用
たとえば食事づくり。毎日しっかり手をかけるのは理想だけど、現実はなかなか難しいですよね。
そこで我が家ではらでぃっしゅぼーやの食材宅配を使い始めました。
農薬や添加物に配慮された野菜や加工品がセットで届くので、「安心」と「時短」が両立できるのがとても助かっています。



食材宅配サービスは家事の負担を減らす(時短)大きな味方!まいた家では大活躍してます!
まずは、超絶お得なおためしセットから始めることをおすすめします!



おためしセットはどれもコスパ抜群なので、頼んで損は絶対しないよ!色々試してみてね!
・Oisixのミールキットはお店の味を誰でも簡単に再現できます!時短を求めている方にも特におすすめ!
・らでぃしゅぼーや, 坂の途中は野菜の品質や美味しさにこだわりたい方に特におすすめ!
初めての方はおためしセットで手軽に試せるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
よくある質問Q&A
Q:おむつ無し育児はいつから始めるのがいい?
A:新生児から始めることも可能ですが、我が家では少し育児に慣れてきた生後1ヶ頃から始めました。明確な決まりはありませんが、首が据わってからの方が排泄姿勢を取らせやすいので楽だと思います。
Q:外出先ではどうするの?
A:まいた家では外出時は準備や処理も大変なため紙オムツを履いていました。ポータブルトイレや多めの着替え、トイレットペーパーを持参するという手もありますが、負担が大きそうなのでまいた家ではやっておりません。
まとめ
おむつ無し育児は、最初はハードルが高く感じるかもしれませんが、ゆるく取り入れるだけでも赤ちゃんとのつながりを実感できます。
「100%成功させよう」ではなく、「赤ちゃんの気持ちを知るツールのひとつ」として楽しみながら取り入れてみてください。
以下の記事では、まいた家で実践している他の育児術についても紹介しているので、よかったら読んでみてください!
ブログランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。
にほんブログ村

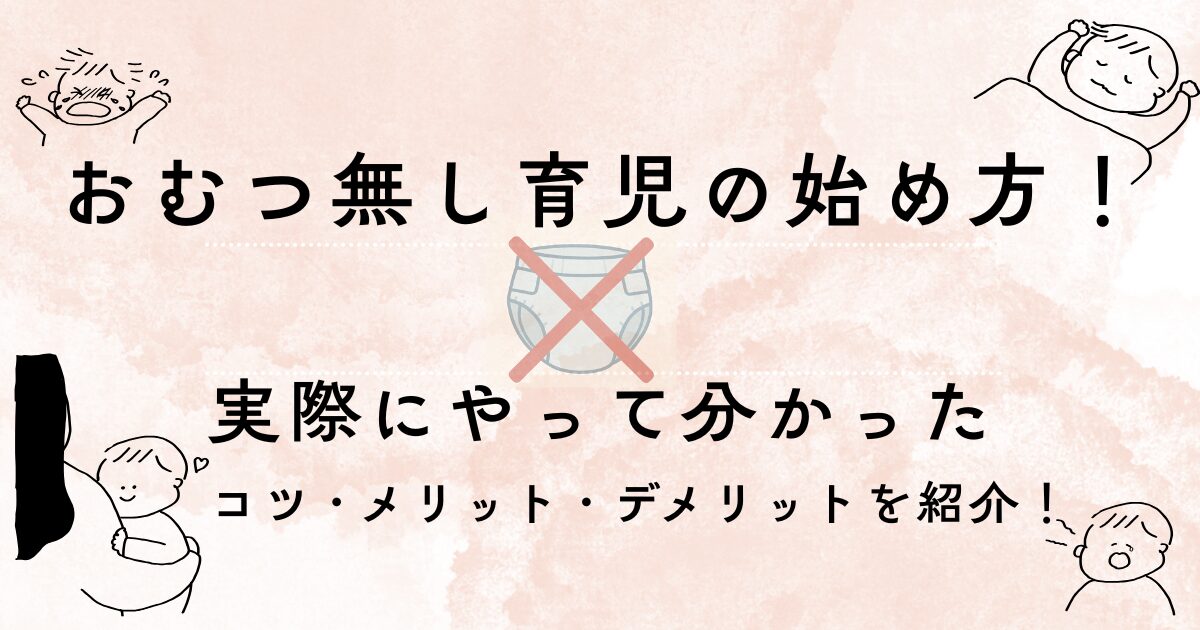


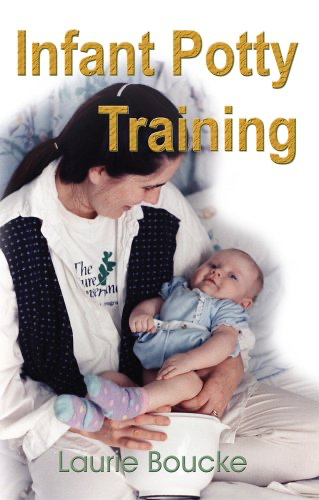
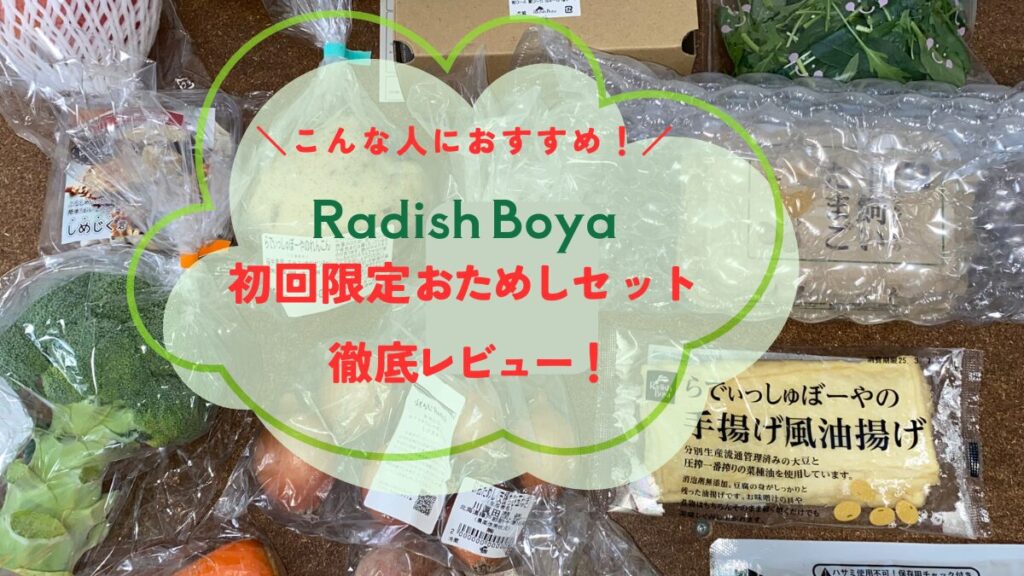

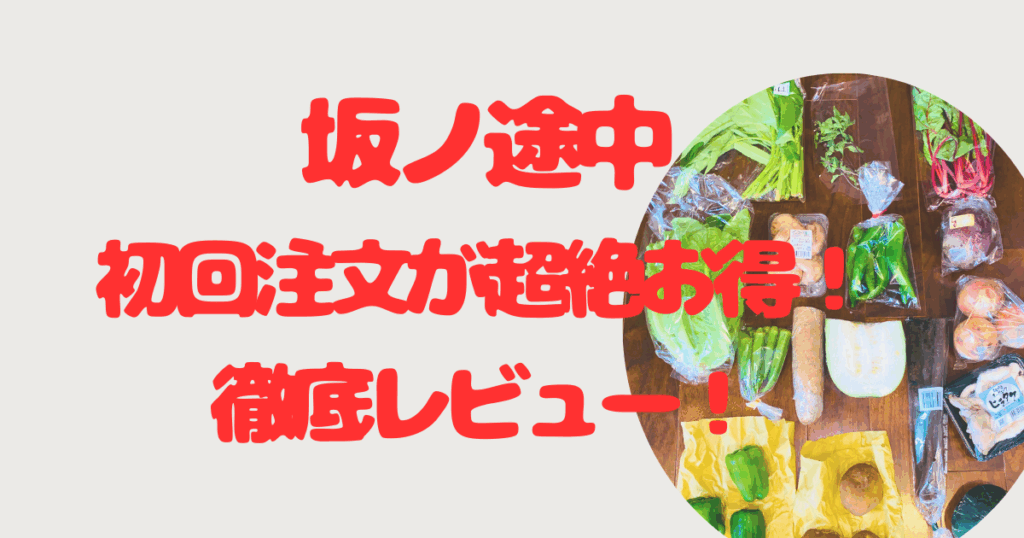
コメント